●アイカム50周年企画「30の映画作品で探る”いのち”の今」
第17回 医薬の思想史 病といのちへの先人たちの問いかけ <2021年4月10日(土)>
第17回 医薬の思想史 病といのちへの先人たちの問いかけ <2021年4月10日(土)>
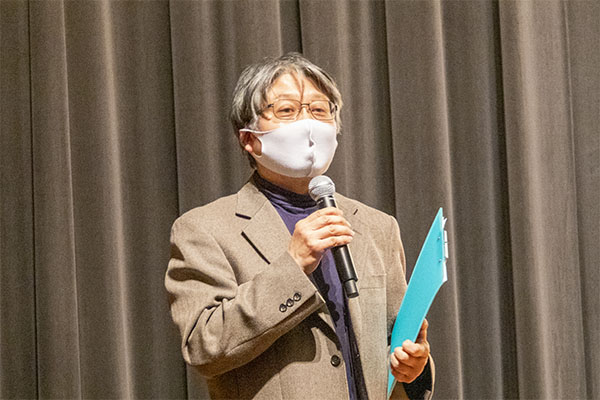
上田:
みなさん、こんにちは。アイカムの50周年映画上映会、今回で17回になります。私は進行を担当します、市民科学研究室の上田といいます。今日のテーマは「医薬の思想史」ということですが、なんで「思想」なんだという問いかけをいただきそうです。でも、考えてみましたら、私たち、薬は病を癒すといいますが、病とはそもそも何なのか、それにどういうふうに対処するのかと問い詰めていけば、私たちの身体や物質の成り立ちとか、社会の仕組みにも関係してきます。それらをどうとらえるかという思想的な問題になってきます。今日の1時間弱のこの映画は、医療、医学の原点に立ち返るような、歴史を遡る映画です。そこからずっと辿って、今、私たちの薬、医療のあり方をもう一回、見直してみようじゃないかという、哲学的な問いかけが含まれています。じっくり見ていただいて、後半は、今日お集まりの方はいつも来ていただいている常連の方が多いようですし、少しつっこんでお話もできればいいかなと思います。
今日のゲストは、公衆衛生学がご専門の山本先生にきていただいています。国際的な経験も豊かな方ですので、みなさんからのご質問を受けて、いろいろなやりとりをしていただけるのではないかと思います。
それでは、川村さん、この映画についてご説明をお願いします。
川村:
アイカムの川村です。今日の「薬へのプロムナード」はアイカムの自主制作映画です。1990年完成、もともとは35mmのフィルム作品ですが、2012年にDVD-Bookとして発売するときに、監督の武田(現会長)が書いた序文から紹介させていただきます。
みなさんもご存知のように、古今東西、さまざまなものが薬として用いられて来ました。そういう草根木皮がなぜ、人の薬になるのかと考えますと、近代科学はとにかくそういうものから有効成分を抽出して、分析して、合成するという道を辿って来たわけですが、例えば、ケシの実は鎮痛薬として使われて来ましたが、その中から鎮痛薬の薬効成分であるモルヒネを抽出しました。しばらくすると、今度は脳の中にも、それとよく似たエンドルフィンという物質があると、これで効くのだというメカニズムがわかって来ました。まあ、たしかにそうなんですが、それが本当にヒトの病を癒すのだろうか。そういう医薬の源流はどこにあるのだろうか、と。
私たちは、長く、生命科学関係の映画をずっと作り続けてきまして、いろいろ考えてきましたが、生き延びることは他の生物も必死に模索してきたと思いますが、どのように生きるのかは、人間でなければ考えない。病を知ることは、いのちを知ることだと思いますし、薬を知ることは人間の証を知ることではないのだろうかと考えました。そういう映画スタッフの尽きない興味が高じて、世界を訪ね歩いたわけです。
映画の中にはいろいろ出てきます。生と死が隣り合った黒死病、ペストの時代を経て、医療と科学が出会ったヨーロッパの医学校の話、そして科学の源流を訪ねて、スピノザに辿り着きました。スピノザは科学精神の源流ではないのか。そのへんは映画で見ていただければと思いますが、ゲーテも、臨床医学を拓いたブールハーヴェもスピノザに惹かれているんです。さらに、アインシュタインまで、と知った時には驚きました。そんなことを考えながら、みなさまもこの散歩道、プロムナードを楽しんでいただければと思います。
みなさんもご存知のように、古今東西、さまざまなものが薬として用いられて来ました。そういう草根木皮がなぜ、人の薬になるのかと考えますと、近代科学はとにかくそういうものから有効成分を抽出して、分析して、合成するという道を辿って来たわけですが、例えば、ケシの実は鎮痛薬として使われて来ましたが、その中から鎮痛薬の薬効成分であるモルヒネを抽出しました。しばらくすると、今度は脳の中にも、それとよく似たエンドルフィンという物質があると、これで効くのだというメカニズムがわかって来ました。まあ、たしかにそうなんですが、それが本当にヒトの病を癒すのだろうか。そういう医薬の源流はどこにあるのだろうか、と。
私たちは、長く、生命科学関係の映画をずっと作り続けてきまして、いろいろ考えてきましたが、生き延びることは他の生物も必死に模索してきたと思いますが、どのように生きるのかは、人間でなければ考えない。病を知ることは、いのちを知ることだと思いますし、薬を知ることは人間の証を知ることではないのだろうかと考えました。そういう映画スタッフの尽きない興味が高じて、世界を訪ね歩いたわけです。
映画の中にはいろいろ出てきます。生と死が隣り合った黒死病、ペストの時代を経て、医療と科学が出会ったヨーロッパの医学校の話、そして科学の源流を訪ねて、スピノザに辿り着きました。スピノザは科学精神の源流ではないのか。そのへんは映画で見ていただければと思いますが、ゲーテも、臨床医学を拓いたブールハーヴェもスピノザに惹かれているんです。さらに、アインシュタインまで、と知った時には驚きました。そんなことを考えながら、みなさまもこの散歩道、プロムナードを楽しんでいただければと思います。
■ 映画 1990 『薬へのプロムナード』 54分

上田:
では、よろしくお願いします。なかなか普段見ないような、いろんなシーンが紹介されていたり、アイカムがいろんな国を訪れて、本当に貴重な歴史的な史料も紹介されていたりしました。山本先生、ご覧になって、いかがですか? 薬学部で教えておられますが、医学生にも知っておいてほしい事柄がたくさん出てきたように思います。
山本:
そうですね。日本では西洋医学に基づいた医学教育が行われ、一部、漢方もありますが、ほとんどは西洋医学に基づいた医薬が使われているわけですが、この映画は本当に科学の源となるような、哲学、医療の歴史、幅広く取材されていて、何度見ても、学ぶところが多いなと思います。
上田:
実際に、こうした歴史や哲学に関わることを、医者や研究者、そして学生さんらが、研究したり、みなさんで取り上げてみることなどあるのでしょうか。
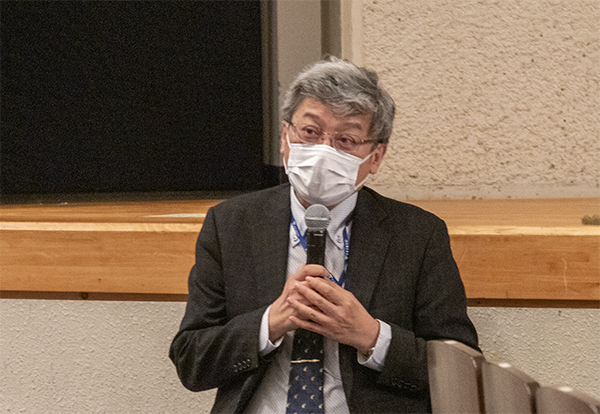
山本:
そうですね、まず、ヒポクラテスの誓いがありまして・・そのギリシア時代から、間の中世などは歴史に残っていなくて、ペストをきっかけに教会の秩序が崩れ、真理を探求しようという哲学が、映画に出てきたデカルトとか、スピノザが、今の医学に繋がるのかなと改めて思いました。
上田:
ちょっと会場のみなさんにも聞いてみましょうか。映画を見た感想なり、聞いてみたいことなど、率直に言っていただければと思います。
薬がテーマではあるのですが、なぜ、今その薬を私たちは使っているのだろうか。それから、薬の使い方について、この映画で扱っていたような問題を意識されたことはあるのかなあ、とか。
薬がテーマではあるのですが、なぜ、今その薬を私たちは使っているのだろうか。それから、薬の使い方について、この映画で扱っていたような問題を意識されたことはあるのかなあ、とか。
■ペストの時代、コロナの時代
山本:
奥深いので、なかなかどこから話し始めたらいいか・・難しいところではあるのですが、スピノザの言われたこと、「自然の法則性を研究することは、恐怖・憎悪・冷酷と戦う手段、考える人間にふさわしい、ただ一つの手段である」。これは今の時代にも非常に参考になるなあと思うのですが。いろんな社会の中に生まれる偏見とか憎しみというのは、科学によって、真理によってしかこれは克服できない、というのは、今でも通じるところがあります。
特に我々、この1年間、新型コロナという全く新しい感染症に直面することになって、いろいろわからないことも多く、一方で感染者に対する偏見とか、いろんなことが起こってきたのですが、今1年経って少しずつわかってきたことで、昨年まで抱いていた恐怖とか怖れがかなり軽減されているかと思うんです。けど、まだやっぱりわからないことがある。このコロナ感染症、一つとってみてもまだまだ真理を求める必要性はある、絶対必要かなと思いました。
特に我々、この1年間、新型コロナという全く新しい感染症に直面することになって、いろいろわからないことも多く、一方で感染者に対する偏見とか、いろんなことが起こってきたのですが、今1年経って少しずつわかってきたことで、昨年まで抱いていた恐怖とか怖れがかなり軽減されているかと思うんです。けど、まだやっぱりわからないことがある。このコロナ感染症、一つとってみてもまだまだ真理を求める必要性はある、絶対必要かなと思いました。
上田:
なるほど。そういうコロナの問題も含めて、いかがでしょう。

TY:
今日は貴重な映画をどうもありがとうございました。先生がおっしゃったように、私も映画を見て、コロナのことと重ね合わせて見ました。結局、わからないこと、社会がどう扱っていくのかということ、やはりマルセイユのペストの時、「人も上陸、ものも上陸、ペストも上陸」。結局、あれは今起きていることと同じことが繰り返されて今でもあるのかなというのが一つ。
もう一つ、近代の医学、学問の医学ですが、昔は江戸時代までは、「体液病理学説」血液、体液の循環が病因となっていたのが、その後、顕微鏡が発明され、「細菌学説」になってしまうと、治療もそうですし、それに対する我々の意識も変わってきているんですよね。身体全体を診ることから、部分で診ることへ。今はもっと進んで遺伝子を見ていこうと、そうなっちゃうと、人間の身体全体を治すということはどういうことなのかが、科学技術が発達すればするほど、わからない世界に入っていってしまう。そんなことを今思いました。
今日は貴重な映画をどうもありがとうございました。先生がおっしゃったように、私も映画を見て、コロナのことと重ね合わせて見ました。結局、わからないこと、社会がどう扱っていくのかということ、やはりマルセイユのペストの時、「人も上陸、ものも上陸、ペストも上陸」。結局、あれは今起きていることと同じことが繰り返されて今でもあるのかなというのが一つ。
もう一つ、近代の医学、学問の医学ですが、昔は江戸時代までは、「体液病理学説」血液、体液の循環が病因となっていたのが、その後、顕微鏡が発明され、「細菌学説」になってしまうと、治療もそうですし、それに対する我々の意識も変わってきているんですよね。身体全体を診ることから、部分で診ることへ。今はもっと進んで遺伝子を見ていこうと、そうなっちゃうと、人間の身体全体を治すということはどういうことなのかが、科学技術が発達すればするほど、わからない世界に入っていってしまう。そんなことを今思いました。
山本:
同感です。映画の中にクロード・ベルナールの「実験医学序説」が紹介されていました。今でも、医学界では、近代医学の幕開けになるような書物と位置付けられると思うんですが、いろいろ分析していく、解剖し、さらにそれを顕微鏡で見る、さらに今では分析してわかるようになった。そうして少しずつ真理を明らかにするようになったというのが、今の近代医学の大きい貢献であったと思います。
近代医学というのは、哲学とか、しっかりした思想体系を基にしているからこそ、世界的に広がった。アラビア医学とか、日本では和漢、中国の漢方があり、世界各地の医療はそれぞれあるのですが、残念ながら、体系化できなかったから、全世界には広がらなかった。しかし、それぞれの伝統医療には、それぞれの文化、地域社会で受け入れる素地はあったわけで、そういうものも大事であるのは事実。特に漢方は日本でもよく使われていますが、ヒトを全体で診るような視点は、近代医学に対する反省として、求められていると思います。
近代医学というのは、哲学とか、しっかりした思想体系を基にしているからこそ、世界的に広がった。アラビア医学とか、日本では和漢、中国の漢方があり、世界各地の医療はそれぞれあるのですが、残念ながら、体系化できなかったから、全世界には広がらなかった。しかし、それぞれの伝統医療には、それぞれの文化、地域社会で受け入れる素地はあったわけで、そういうものも大事であるのは事実。特に漢方は日本でもよく使われていますが、ヒトを全体で診るような視点は、近代医学に対する反省として、求められていると思います。
上田:
西洋近代医学が、体のメカニズムを解明することによって、それに合わせて今の医薬ができてきている。その時に、病気の全体を見るということに必ずしもならない場合があって、そういう場合は、伝統医療が持っている、解明されてはいないかもしれないけど、有効な経験の力みたいなものが活きてくる、という話しですね。
山本:
そうですね。その通りですね。
上田:
コロナのことも少し出てきましたが、率直に言って、これは薬が発達したら、なんとかなるというものとは、ちょっと違う性質の問題だと思うのですが、そのあたり、先生いかがですか?
ペストの流行の時、マルセイユに病原菌が入ってきて、当時は病原菌であることはわからなかったですよね。今はそれもわかって、ウイルスもわかって、なんとかなるという面もあるでしょうけど、いったん流行が始まったら、なかなか抑えられない、ということを私たちは如実に体験しています。なにが医学の強みなんだろうか、弱みなんだろうか。
ペストの流行の時、マルセイユに病原菌が入ってきて、当時は病原菌であることはわからなかったですよね。今はそれもわかって、ウイルスもわかって、なんとかなるという面もあるでしょうけど、いったん流行が始まったら、なかなか抑えられない、ということを私たちは如実に体験しています。なにが医学の強みなんだろうか、弱みなんだろうか。

山本:
映画にも出てきた、感染症のパイオニアだった人たち、フランスのパスツール、ドイツではコッホ、この二人の貢献は大きくて、パスツールの話で「病原体は何もないところからは生まれない」というのがあります。感染症をコントロールするためには、3つの原則というのがあるんです。一つは病原体、一つは宿主、我々です。もう一つは、感染経路。この3つのうち、一つを断てば、必ず感染は止まるというんですね。
一つめの要因、細菌やウイルスなど病原体がなくなれば、感染は起こらないけど、病原体はなかなかなくならない。病原体は殺菌すれば、すぐ死ぬようなものですが、たとえば、食中毒の菌などは熱湯をかければ必ず死にますので、広がらない。でも新型コロナウイルスは世界中いろんなところに広がっているので、なかなか不活化することは難しい。一方で、宿主側の要因として、我々の免疫が十分にあれば、排除することができる。これも自然に獲得するものもあるし、人為的に獲得するのは、予防接種が有効であれば、これでも排除することができます。
もう一つの感染経路は、これは実際、最近、距離を取りましょう、マスクをしましょう、と、病原体が移る経路を完全に断つことができれば、遮断できます。
三つのどれか完全にできれば、遮断できるんですけど、新型コロナの場合、どれもまだ、完全にはできない。今、期待しているのはワクチンです。特に宿主は、コロナウイルスの場合、基本的にヒトだけですね。厄介なのは動物を介するものですが、犬とか猫には感染しないと言われているので、比較的、対策は立てやすい。ワクチンができれば可能性は高い。みなさん天然痘はご存知ですか。天然痘は、ヒトからヒトにしか感染しない、動物の中間宿主がいなかったから、ワクチンを一人残らず打つということで、完全に撲滅できました。天然痘ウイルスは、今、自然界には存在せず、ごく限られた研究所で厳格に管理されています。これは万が一、再発した時にワクチンなど作るためにどうしても必要なので保管しています。コロナウイルスも基本的にヒト-ヒト感染なので、天然痘のように撲滅できればいいのですが、ワクチンに期待です。
上田:
基本原則は見えていて、手の打ちようはあるんだけど、なかなかそうはいかない、と。
山本:
あとは敵も賢いもので、薬剤耐性のことは映画でもよく説明されていたように、細菌の場合は耐性菌になるとか、少し違いますが、ウイルスも少しずつ変化して、ワクチンを逃れて生き延びるとか、いろんな薬が出てもかいくぐるとか、耐性ウイルスが出る可能性もあるので、コロナの場合も敵はなかなかなものです。今、第四波とか、新しい変異ウイルスも出てきていますから、まさに変化しつつあります。
■生と死の隣り合うところから
TT:
私は、薬学は勉強してなくて、専攻は主にバイオテクノロジーなんですが、まず、この映画を見て、「我思う、ゆえに我あり」ということがヨーロッパを中心に支持されていた理由として、やはりペストの影響で、街のいたるところに、亡くなった人の死体があるのと同時に、肉市場があって、動物の食用の死体が同時にあるところを日常的に見るとなると、やはり、人間と動物は、肉体としてはあまり違いはないのかな、というのは感じました。で、そうなったら、動物と人間が、何が違うかとなったら、やはり精神の部分、思考の部分と考えるのは自然の流れかなと思って、この映画を見せてもらって、哲学の流れが自分の中で感じることができて勉強になりました。
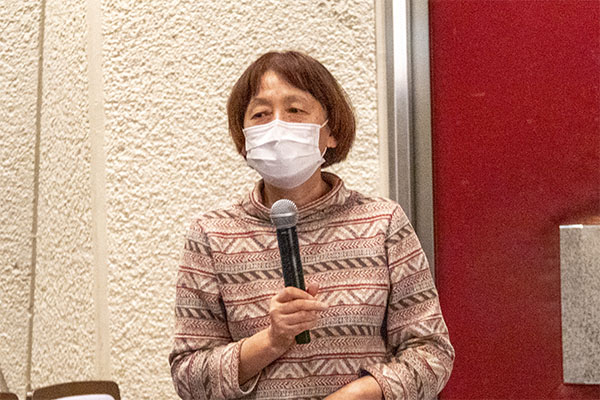

川村:
いま、思い出したのですが、撮影のために、パリの真ん中、イノサン共同墓地に隣り合って肉市場があった跡を訪ねると、噴水広場があり、すごく大きなショッピングモールが建設中でした。で、現代の食肉市場はというと、パリ郊外のランジス市場、ヨーロッパ一か世界一、空港みたいな広大な敷地に巨大体育館のような建物群が立ち並ぶ、ものすごい規模でした。また、日本人の感覚からすると不思議だったのは、サン・ドニ聖堂にある彫像。自分の生前の礼拝像を作るのはわかるとして、その下に、死後硬直も生々しい彫像を飾るという感覚です。ペストの時代には、メメント・モリという、死を想えとか、死に対決するという発想があったようですが、これはまさしく心身二元論で割り切っているということなのか。
そして、科学精神の源流としてスピノザに辿り着いたのですが、デカルトの心身二元論に対して、スピノザは心身一元論なんですね。デカルトが心身を分けたことで科学は進んだと思われている向きもあるけど、スピノザは心身を分けない、ある意味、汎神論。「自然に内在する法則性を神と呼び」スピノザは追求する。また、ゲーテはスピノザを支持して、「全体を見るように部分をながめよ。内にあるものもなければ、外にあるものもない、内がそのまま外なのだ」というわけですが、それは、ニュートンの近代科学、自分の外に考えた理想的な絶対空間・絶対時間の中で成り立つ物理法則ではなくて、それを超えて、自分もその中に入れて考える現代科学にも通ずる、だからアインシュタインにもつながっているのかなあと、なんとなく納得したのですが。
上田:
おもしろいですね。
山本:
映画の最後の方に、脳の話がありましたよね。古くは、魂があって、体とは別だと思われていたけど、最近では、いろんな高次機能、神経活動も、神経伝達物質があって、ニューロンがあって、病気もわかるようになってきました。今は精神と身体活動、脳の活動は独立ではないとされていますので、哲学的な考え方と今の科学の考え方はこれからの課題かなと思います。
■科学的に考えること 数字・統計・薬の有効性

TA:
たいへん興味深い映画でございました。医師が治療した方が悪化したり、死亡する人が多かったという話に、びっくりはしたんですが、ただ冷静に考えてみると、そういうところを経たからこそ、いろんな医術も医薬も進歩してきたんだなと思って、非常に持っていた知識がひっくり返って、とても意外には思ったけど、もっともだと思って納得しました。
山本:
あの治療した方としない方という話では、治療した方の死亡率が高かったということですが、数字で比較して見て、初めてわかった話で、数字で出す、数学の発想がなければ比較できなかったことです。これも後からわかったことで、いろんなことを数値化してみる意味で、科学の真理に照らすことが必要なのだと思います。
それと誤解のないように言っておくと、これは数の比較ですが、治療した人・しない人で、おそらく重症な人に対して一生懸命治療して、軽症な人はあまり治療しなかったからだとも考えられます。
で、今では、そういう薬が効くか・効かないか、治療が効いたか・効かないかは、みなさん、プラセボということを聞いたことがありますね。今のコロナのワクチンでも、本当に効いたか効かないかを調べるのに、本物と偽物、プラセボといいますが、これを投与します。治療した側もどちらを投与したかわからないようにして、プラセボと比較して本当に薬として有効なのか。本当によければ初めて新しい薬として認められます。そういう意味で、もとの状況を比較してやることがとても大事です。
それと誤解のないように言っておくと、これは数の比較ですが、治療した人・しない人で、おそらく重症な人に対して一生懸命治療して、軽症な人はあまり治療しなかったからだとも考えられます。
で、今では、そういう薬が効くか・効かないか、治療が効いたか・効かないかは、みなさん、プラセボということを聞いたことがありますね。今のコロナのワクチンでも、本当に効いたか効かないかを調べるのに、本物と偽物、プラセボといいますが、これを投与します。治療した側もどちらを投与したかわからないようにして、プラセボと比較して本当に薬として有効なのか。本当によければ初めて新しい薬として認められます。そういう意味で、もとの状況を比較してやることがとても大事です。
上田:
なるほど、そうなんですね。
山本:
もう一つ補足すると、医療行為をしたために、却って悪いという例もあります。みなさん、ナイチンゲールという方を知っていますね。白衣の天使で有名ですが、実は、ナイチンゲールは統計のことにすごく詳しい方で、クリミア戦争の時、従軍して、きちんと記録をとってどういう状況で患者さんが亡くなったかを調べました。人が出入りするところと出入りしないところで、出入りした方の病棟では、院内感染を起こして、却って病気の発生が高くなっているとか、いうことを導き出しているんですね。今でこそ、院内感染とか言われていますが、当時はそういう概念はなかったので、治療して却って悪くなったということは、実は、昔もないことはなかった。ですから、本当に何が効いているのか、何が悪いのか、本当にいろんな条件をきちんと整理して分析する。これが今の近代医学ということで、ニュートンとかデカルト、哲学者とか数学者、医学、薬の開発にもこういったことが活用されている。大切なことだと思います。
上田:
ナイチンゲールの話もでましたが、実は、医学の歴史を勉強すると、昔は治療するときに医者たちが消毒をしなかったということがあって、そのために分娩を通じてたくさんの人が産褥熱で亡くなったということが書いてありました。そのとき、修道院で分娩した人の方がずっと亡くなる方が少ないということに注目した医者がいて、やはり手洗いが有効だということを見つけたという歴史がありました。そこから、消毒ということが広がったとか。言ってみれば、ちゃんと統計的に比較して、その原因を探っていくという方法があったということですよね。それは山本先生が従事しておられる公衆衛生の方で、重要な方法になっていますね。
山本:
そうです。

ST:
私は眼科医ですが、慈恵医大の校訓として、「病気を診ずして、人を診よ」という言葉がありまして、患者さんの人生のこれまで、これから、家族のこと、いろんな人間としての背景を考えて診療に当たりなさい、というのが、臨床に出る医師に対して、あるいは医学生に対する教育の言葉として語り継がれてきたのですが、この映画を見ていると、病気の根絶をするためには、「病人よりも病気を診ない限りは、患者は救えない」という。病気そのものを知るところからまず始めないといけないとありまして、なるほど、たしかにそれもそうだなと。病気ばかりを診るのも問題だけど、人ばかりを診ていても、そもそもの病気をちゃんと知らないといけないと思いました。
統計学のお話もありましたが、何年か前に、カタリンという商品名で市販されていた白内障の目薬がよく効くというのでみなさん安心して使っていたんですが、統計学の手法で処理すると、薬として認可された頃の生データに現在の統計学にはふさわしくないデータが混じっていて、計算し直したら、有効性が否定された大事件があり、新聞やテレビでも取り上げられました。客観的なデータを集めて正しく解析していくことが本当に大切なのだと、つくづく感じた次第です。
私は眼科医ですが、慈恵医大の校訓として、「病気を診ずして、人を診よ」という言葉がありまして、患者さんの人生のこれまで、これから、家族のこと、いろんな人間としての背景を考えて診療に当たりなさい、というのが、臨床に出る医師に対して、あるいは医学生に対する教育の言葉として語り継がれてきたのですが、この映画を見ていると、病気の根絶をするためには、「病人よりも病気を診ない限りは、患者は救えない」という。病気そのものを知るところからまず始めないといけないとありまして、なるほど、たしかにそれもそうだなと。病気ばかりを診るのも問題だけど、人ばかりを診ていても、そもそもの病気をちゃんと知らないといけないと思いました。
統計学のお話もありましたが、何年か前に、カタリンという商品名で市販されていた白内障の目薬がよく効くというのでみなさん安心して使っていたんですが、統計学の手法で処理すると、薬として認可された頃の生データに現在の統計学にはふさわしくないデータが混じっていて、計算し直したら、有効性が否定された大事件があり、新聞やテレビでも取り上げられました。客観的なデータを集めて正しく解析していくことが本当に大切なのだと、つくづく感じた次第です。
山本:
コメントありがとうございました。まさにその通りで、私は公衆衛生の分野にいるんですが、薬が効かないとか、統計分析とか、日本では、集団に対して実証的に示したのが、高木兼寛さんです。森鴎外さんは陸軍の軍医で、高木兼寛さんは海軍軍医でした。明治時代当時、脚気が多かったんですね。その脚気の原因が、細菌とか病原体だという考えが支配的でした。だけど、高木兼寛さんは実証的な人で、白米をやめて玄米を食べさせたら脚気にならないことを見出して、当時、ビタミンなど発見される以前でしたが、彼はいち早く、海軍では白米をやめて玄米を取り入れ、脚気を根絶しました。数字が大事だという話ですが、まだよくわかっていないものに対しては、未然に手を打つことも大事です。
高木兼寛さんは慈恵医大を創設、医療人を作るところで始まっている歴史もあるわけでして、今日の映画は、主に西洋の歴史でしたが、日本の医学界、いろんな先人の活躍もあり、いろんなことを経て現在に至っている。
目薬の話もありましたが、今、新しい薬は、前にある薬よりも良くないと認めてもらえない。同じではダメで、統計的により良いものであれば、初めて認められる。そこで、だんだん薬の値段が高くなっている。試験で言えば60点で良かったのが、新しい薬は70点、80点でないといけないとなると、より良い薬を作るには、良さを出すためにはコストも高くなる。一方で、認知症の薬も以前はたくさんあったのですが、あまり効かないということがわかって、多くは薬として認可を取り消されています。
今、新しい薬を出すということはたいへんなんです。
高木兼寛さんは慈恵医大を創設、医療人を作るところで始まっている歴史もあるわけでして、今日の映画は、主に西洋の歴史でしたが、日本の医学界、いろんな先人の活躍もあり、いろんなことを経て現在に至っている。
目薬の話もありましたが、今、新しい薬は、前にある薬よりも良くないと認めてもらえない。同じではダメで、統計的により良いものであれば、初めて認められる。そこで、だんだん薬の値段が高くなっている。試験で言えば60点で良かったのが、新しい薬は70点、80点でないといけないとなると、より良い薬を作るには、良さを出すためにはコストも高くなる。一方で、認知症の薬も以前はたくさんあったのですが、あまり効かないということがわかって、多くは薬として認可を取り消されています。
今、新しい薬を出すということはたいへんなんです。
上田:
現在の薬の抱えている大きな問題ですよね。おそらくみなさん、薬というものは、開発されて使えば、効くと信じて、使う側も使われる側も、やっているものなんですが、結果的に社会全体としてみたときに、それが何をもたらすのかを考えたら、本来、薬にあまり頼ってはいけないところを、それだけに頼ろうとしている、ということも起こってしまう。そういう意味で、私たちは歴史のようなことも意識しながら、良い薬の使い方とは何かを考えていかなくてはならないということですね。
山本:
本当にそうですね。
■薬を求めて

KK:
非常におもしろい切り口で見させてもらいました。ありがとうございます。
ただ、哲学的な部分と、近代医学の部分と、特にヨーロッパの場合は、宗教的なキリスト教がベースに入って、哲学が成り立っている。そのときに、ちょっとギャップがあるように感じました。病気に対する哲学的な部分と、近代医学的での病気への対応、まあ薬ですよね。むしろ、キリスト教的な部分がない方が近代医学としてもっと進んだのではないかという印象がしましたが、そういうことはないでしょうか。
ただ、哲学的な部分と、近代医学の部分と、特にヨーロッパの場合は、宗教的なキリスト教がベースに入って、哲学が成り立っている。そのときに、ちょっとギャップがあるように感じました。病気に対する哲学的な部分と、近代医学的での病気への対応、まあ薬ですよね。むしろ、キリスト教的な部分がない方が近代医学としてもっと進んだのではないかという印象がしましたが、そういうことはないでしょうか。
上田:
難しい問いですね。先生、いかがでしょう。
山本:
それは非常にごもっともです。今日の映画でもありましたが、ギリシア時代、ヒポクラテスの時代から後、西暦200〜500年からの特に中世のヨーロッパは、キリスト教のもとで科学に対して非常にネガティブな時代が続いたということがあります。科学の基礎は、武田会長などが取材されたアラビア圏の方が、中世はヨーロッパよりも進んでいた。例えば、アルコールという言葉ももともとはアラビアから、ゼロという概念もインドで生まれている。ヨーロッパはペスト騒動などで、中世のキリスト教の権威に対する反動が起こったと言われています。それが、今、歴史的な評価ですよね。宗教革命があり、産業革命以降、ようやくヨーロッパで科学が進むようになったと私は理解しているのですけど。

TT:
薬学について質問ですが、ゴキブリとか、サソリとか、いろいろな動物が生薬市場に並んでいましたが、インターネットなどない時代は、情報が拡散するということはあまりなくて、速くはなかったと思うんですけど、薬を作るにあたって、この病気にはこの動物が効くということは、どういうふうに広がっていくのかな、と疑問に感じました。
上田:
なるほど、おもしろいですね。
山本:
非常にもっともな指摘ですね。今でこそ、何か疑問があれば、ネットで調べれば・・(笑い)、すぐに何か出ますけど、人の流れしか頼るものはなかったわけで、電話もできる前は、これは効きそうだとかいうのは、紙に書いたものとか、人伝てにしか伝わらない。
ホメオパシーとか、薬箱でこれとこれとを・・昔はこうしていたのかと、私も改めて見ましたけど、最近だったら、スーパーコンピューター使って、既存の薬と化学物質の構造を見て、これとこれを組み合わせてとかシミュレーションしているらしいですけど。
ホメオパシーとか、薬箱でこれとこれとを・・昔はこうしていたのかと、私も改めて見ましたけど、最近だったら、スーパーコンピューター使って、既存の薬と化学物質の構造を見て、これとこれを組み合わせてとかシミュレーションしているらしいですけど。
上田:
ただ、私も詳しくはないですけど、人間の往来という意味では結構ありますよね。映画でも西洋医学が各国にどういうように広がったのか、蘭学の時代に、オランダとのつながりを通して、医学が日本に入ってきたということがありました。ですから、時間はかかったにしても、確実に広がっていく手段を世界は持っていたという気はするのです。
山本:
特に大航海時代とか・・ライデン大学から、広く長崎まで伝わった医学の話も感慨深く伺いました。

YN:
今日は貴重な映画とお話、ありがとうございました。やはり、一番の関心は、今のコロナ禍がどう終息するのか、ということで、ワクチンも期待するのですが、やはり治療薬も、どうやら今薬の開発が置かれている状況が厳しいものだと初めて知りまして、なかなかできてこないのもそういう状況なのかなと思いました。やはり手軽に、治療できる仕組みとか施設ができればいいなあと思っています。
山本:
ありがとうございます。これは本当に、今日の映画で、ケシの実からオピオイドという物質ができたという話がありました。2015年にノーベル医学生理学賞を受けられた大村智先生のイベルメクチンという薬がありますが、あれは土の中のカビから作り出された薬です。あの薬は世界中で使われている薬で、寄生虫症に使っている薬ですが、これがコロナウイルス感染症に効くかもしれないというので、注目を集めています。イベルメクチンをコロナのいろんな患者さんをステージごとに分けて、いろいろ分析してみる、効いたということもあるけど、残念ながら、効いたとは言えない情報もあって、なかなか認可まで至っていない。
みなさん、オプジーボという薬を知っていますか。これもノーベル賞ですが、これなどは1錠数万円もする薬です。一方、イベルメクチンは非常に安い薬で、これが本当に効くなら、すごくいいんですけど、なかなか白黒決着は付いていない。治療薬の方は、そのほかにもアビガンとかいろいろ候補はありますが、優位性をプラセボと比較して、まだこれという切り札が見つかっていないんです。
みなさん、オプジーボという薬を知っていますか。これもノーベル賞ですが、これなどは1錠数万円もする薬です。一方、イベルメクチンは非常に安い薬で、これが本当に効くなら、すごくいいんですけど、なかなか白黒決着は付いていない。治療薬の方は、そのほかにもアビガンとかいろいろ候補はありますが、優位性をプラセボと比較して、まだこれという切り札が見つかっていないんです。
上田:
そういう中で、私たちに求められている対処は、うまく効くものを探していって、薬を作っていくというのも一つですが、もう一方で、コロナにかかったらすぐ重症化する人もいれば、そうでもない人もいる、症状の出ない人もいる。多様な状況が生まれていますが、その原因を明らかにして、どうしたらいいのかという見通しをもっていくのもいいのでしょうけど、現代の医学をもってしてもそれは難しいかもしれない。そういうことを今、見せつけられている気もします。
山本:
そうですね。人間の都合のいいようにはいかないというのを見せつけられている気もします。
■死生観 私たちはどう生きるか
TA:
興味深い映画でしたが、昔の病院が、治療する施設ではなくて、死を待っていたということもすごくショッキングでびっくりしました。


山本:
今日の映画でも出てきたホスピスとか、ホスピタリティやホテル、人を収容するという意味で使われていますが、日本の病院と違って、西洋の病院は教会がベースになっています。日本だと薬師が自分の家で治療したという点で、医療の起源が、日本とヨーロッパではかなり違っていると言えると思います。
上田:
なるほど、そのへん調べてみたら、いろんなことがわかってくると思いますが、少なくとも、私が感じていることの一つは、中国の医学が日本に伝わって、患者さん、病人を診るときに、西洋のような体制を作ったかというと長くそうではなかった。そのときに本草学、薬草を使って対処している。では、医学として確立した科学的な体系に基づいて治療していたかというとそうではないですが、実際に経験的に得てきた知識を積み上げて、いろんな処方を出していく、それで有効な面が確保されていたという歴史があります。そういう意味で、西洋近代医学の持っている強みと、各国の文化を経て、築いてきた経験的な知恵みたいなものがあったのではないかと思います。必ずしも、西洋近代医学が主流になったからと言って、それで全部覆い尽くせるものではないなという気もするのです。
あと、日本人の持っている生命観みたいなものと、西洋近代科学の基にしている生命観は必ずしもしっくりしないこともありますよね。人が亡くなることに対して、もっと時代を遡れば、今みたいにバタバタ騒がずに、従容として死を受け入れるということも根付いていたような気もします。その中で、医療者は西洋医学の原則に立つということで、昔ならば、家で家族に看取れながら亡くなるのが当たり前だったのに、今はみんな病院になってしまっているのが象徴的ですけど。なにか少しずれているなあと思います。
あと、日本人の持っている生命観みたいなものと、西洋近代科学の基にしている生命観は必ずしもしっくりしないこともありますよね。人が亡くなることに対して、もっと時代を遡れば、今みたいにバタバタ騒がずに、従容として死を受け入れるということも根付いていたような気もします。その中で、医療者は西洋医学の原則に立つということで、昔ならば、家で家族に看取れながら亡くなるのが当たり前だったのに、今はみんな病院になってしまっているのが象徴的ですけど。なにか少しずれているなあと思います。
山本:
たしかにそうですね。死は全く別物になっている。今の世の中で、死は全くアンタッチャブル、死について語ることはタブーになっている。家の中で人がなくなることも避けられてきた。
上田:
どうですか? いろんな国に行かれて、そういう医療活動を見てこられて、死生観が違うのではないかとか。
山本:
あると思います。特に日本は、伝統的な東洋的な哲学や、社会の規範があって、その上に西洋的な考え方や日本独自の発展もありますから、それぞれどこの国に行っても違うと思いますね。
今、在宅医療というのが、どこの国でも提唱されています。施設に入って治療するのと、できれば、家で治療するというのに分かれていますので、それぞれの死生観によって、それぞれの国でいろんなシステムができつつあると思います。
今、在宅医療というのが、どこの国でも提唱されています。施設に入って治療するのと、できれば、家で治療するというのに分かれていますので、それぞれの死生観によって、それぞれの国でいろんなシステムができつつあると思います。
上田:
大変おもしろいのは、医療そのものは生死を扱うのですが、生死そのものは医療だけにとどまらない、人間が長く持ってきた観念にも関わりますから、そういう意味で、宗教の問題がなんらかの形で、ある意味、プラスに作用したり、マイナスに作用したりすることが起こってくるということでしょうね。

山本:
いまの医療現場では、コロナの関係で困っていることとして、従来、亡くなるときに家族に看取られて亡くなる、葬儀にしてもご遺体の手を触ったり、友人・知人が集まってお別れの儀式があったのが、このコロナによって、随分形が変わりつつある。たとえば、病室に家族が来られないこともあって、死んだ人はそんなにウイルスを出すはずもないのですけど、科学的根拠のないまま、恐れている。今まで葬儀は、生と死の、特に死後の死者とお別れする、生物的な死とは別の、社会的な死の受容の意味があるので、これからのポストコロナというか、まだ終わっているわけではないですけど、コロナの時代をどう生きるか、が問われているかと思います。
上田:
まさしく、今日の映画の話題につながることが、私たちの現実の問題として出てきている一つの例ですね。山本先生、長時間、ありがとうございました
イベント感想はこちらへ
mail:event@icam.co.jp TEL:03-6905-6610 / FAX:03-6905-6396
